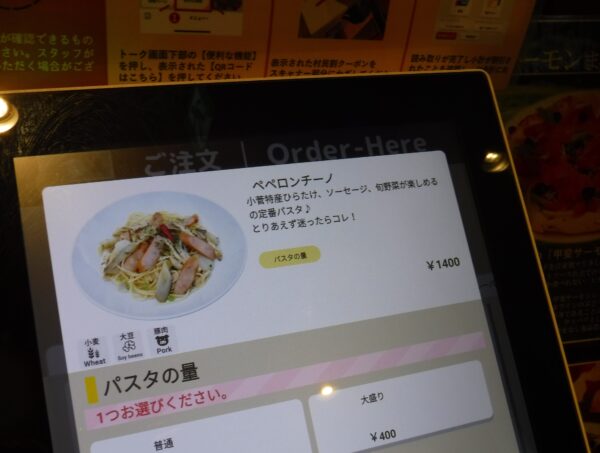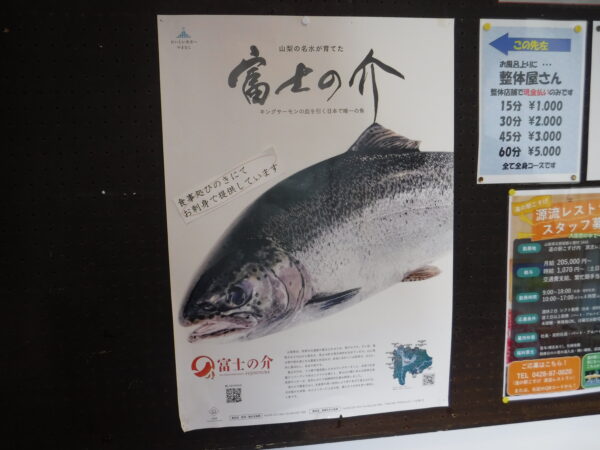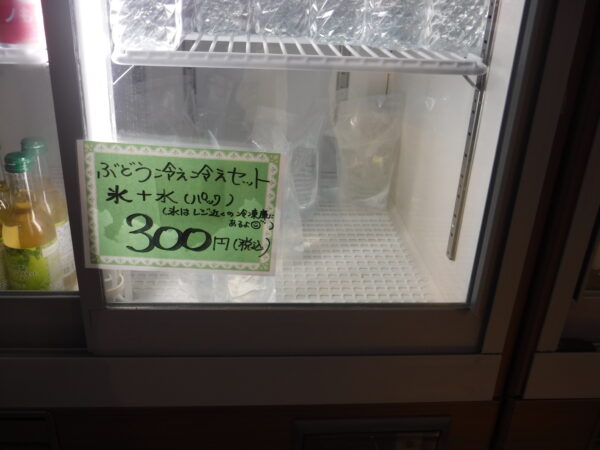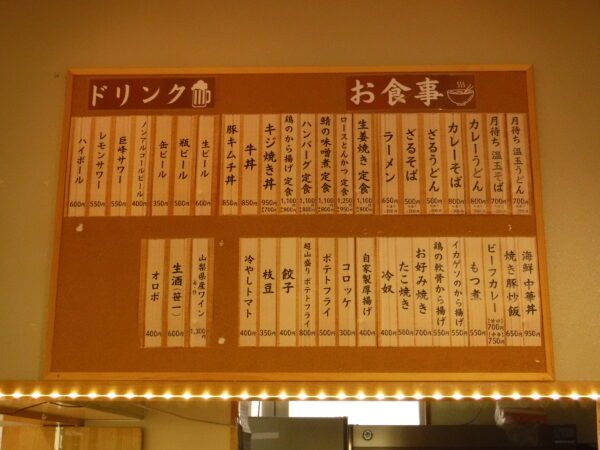一面に並べられたソーラーパネル。
これが将来、エネルギー不足という事態を迎えた折、ソーラーパネルありがとうとなるのか、やっぱり無用の長物だったとなるのか。
現時点でわからないこと。それはソーラーパネルというものを応援すればいいのか、否定すればいいのかということ。
見た目にはやっぱり良くない。
本来は、荒地で草でボーボーなはずのところ、きっちり長方形に切られた、精密な、正確無比なパネルがきれいに並べられている。
これがなんとも気持ち悪いと感じるのは、人間感覚ならではなのだろうか。
人間以外の動物たちはこれを見てなんと感じているのだろうか。
どのような目的を持ってこのような区画を作り上げたのだと思っているのか。
まさかこれが「遊び」のためだったなんて言えるか。
スマホでゲームをする。好きなテレビを見る。好きな音楽を聴く。娯楽施設へ出掛ける。
現代人の遊びに電気は不可欠だ。
遊びそのものに電気を使うことはもちろん、ガソリンスタンドの利用など、間接的に電気のお世話になっている場合もある。
しかもその対象は広く。大人から子供まで。これは運転免許を持ってあちこち自由に行けるわれわれ大人だけに限ったことではない。
幼稚園児、保育園児、小学校の低学年だって、今や電気が無いなどという条件下では刺激的なエキサイティングな遊びができなくなっている。
子供一人遊ばせるのにスマホが無くてはならない。
親が子の小さな手にスマホを乗せてやる。
図らずもスマホゲームの英才教育。
小さいうちから、遊び=機器を使ってやるもの。で、叩き込む。
そのうち大人から子どもまでみ~んなスマホゲームのお世話になる。
そんな社会が形成されつつある。
ぜいたくは敵だ。
そんな戦時中のスローガンよろしく、人間生活最低限のためのエネルギー利用に切り替えられるならば苦労はない。
やはりそれはムリだろう。
自身だってすでに知ってしまっている。電気を使った遊びを。だから手放せない。そして、どうやらこのことは今後の人生においてもずっとつづくのだということが確定的となっている。
それでもまだ理性的なコメント。ネット上にはそんなコメントが多い。
「発電所を作るなー!」
電気をつかって書き込まれたコメント。
きわめて理性的な行為であると思う。
環境問題どうしたいのか。という問いに対して。
自身は、もう理性的に立ち向かうことをやめることにした。
飽きっぽい性格の持ち主には合わないやり方だと思ったからだ。
それよりも、人々がもともと持っている快楽や欲望というものに訴えかけることにした。
そのほうが人は動いてくれるかもしれない。
今回もまた、堤体前に行って歌ったというエピソードを投稿する。
歌える堤体さがしの旅。
2025年最後の投稿である。

昭和生まれ
12月28日、午前8時25分、山梨県北杜市白州町白須。
スタートはコンビニの駐車場。
気温はマイナス3度。
ピリッ!とした寒さに耐えながら、冷たくなったデジタルカメラを握る。
南の美しき山は雪をかぶっている。甲斐駒ヶ岳だ。
北の美しき山も雪をかぶっている。八ヶ岳だ。
駐車場となりのソーラーパネル地帯は雪をかぶせてはいないが霜が降りている。
すでに朝日はのぼっていて、その霜の降りたソーラーパネル地帯を太陽がジリジリと照らしている。
こんなふうにパネルを霜が覆っているようでは発電効率が悪いはず。管理人を呼んであげて、水を撒くなりワイパーで削るなり霜を除去するような何らかの処置をしてあげたほうがいいように思える。
几帳面だと言われる日本人の性格とソーラーパネルの管理とが合ってない。洗車大好き日本人を以てして、ここはノータッチということなのだろうか。
それもそのはず、ここには管理人がいない。無人なのだ。
こんな無人施設を発電所というのだから時代は変わったものだ。
仕事がら山に向かう機会に恵まれているが、建設現場だって、キャンプ場だって、ごみ処理場だって、土産物屋さんだって「人」というのは必ずと言っていいほどいるもの。
みんなどこの施設も営業していないのかな?なんて横を通ると、事務所の蛍光灯がポッと点いていて人の気配に安心するものなのである。
やっぱり人だ。人。
AIというものが人並みに仕事をしてくれる時代が来るという。
果たしてそれらが非常事態発生時にきちんと作動してくれるのかどうか。
人だったら、まさに人道的感覚をもって物事に対処してくれるような気がする。だから人のほうが安心だと思っている。
昭和生まれの悲しい性か?



武川米
午前8時45分、コンビニを出発。
午前8時50分、道の駅はくしゅうに立ち寄る。
店内、広いスペースには地元産の野菜がならぶ。産地は釜無川右岸地域である白州、武川。ほか、釜無川左岸地域である小淵沢、長坂、大泉、高根、須玉、明野。
山梨県産の農産物といえばもも、ぶどうの2大果物をイメージするが、旧北巨摩郡武川村を擁する北杜市は稲作のさかんな地域だ。
当地のブランド米「武川米」は日本国内でも最高級の米とされ、もともと高値で取引されてきたもの。
今年も昨年にひきつづき米の価格が高騰した。日本人の主食をになう製品が、まさかこれまでの値段の倍以上になろうとは、だれもが予想しなかったことであろう。
今や新米5キロ¥4000円と聞いて、高いのか安いのかがよくわからない。新米であるから珍重されなければならないのは確か。しかしながら、それで¥4000円ですと言われて、値段をつり上げられているのか、適価なのかがよくわからない。
米の値段だけは本当に相場がわからなくなってしまった。
こんな時は、いっそ一番のものを口にしてみるのもアリかもしれない。感覚が麻痺したような今だからこそ、最高級品に手を出すのもこわくない。
最高級品は迷わない。なんてったって「コシヒカリ」じゃなくて「農林48号」とかいうなんともなんとも意味ありげな、サイケデリックな名前が付いているからだ。
今日はこれくらいで勘弁しておいてやる!
「新米」のシールが貼られていたいなり寿司にした。
2キロ¥3000円オーバーという超高級価格にチビッたわけでは無い。すぐに食いたい。どこで口にするかがウマい、ウマくないの別れ道となるからだ。
堤体前でのお楽しみに購入。どこで食うのがウマいかって、それはやっぱり堤体前ということになる。








尾白の湯へ
午前10時10分、道の駅はくしゅうを出発。
太陽がだいぶ高くなってきた。しかし、まだまだ寒い。
寒さの解決方法は?
温泉!
尾白の湯をめざす。
「白州農協前」の信号交差点から西進。「シャルマンワイン」「しろきや」といった看板を見ながらすすむ。ハッピードリンクを過ぎて、道なりにそのまますすむと北杜市立白州中学校のグラウンドわきへ。
白州中学校グラウンドわきを過ぎたところで右折すると昨年も来た「べるが通り」に。
眼前に見える山に向かって長い長い直線道路をツッ切ると尾白川渓谷方面。直線道路の途中、ひだりに曲がると大武川方面。
いずれの川に入るにしても、まず体を温めたいなら「尾白の湯」へ。尾白の湯はべるが通りの南側に位置するので左折する。
ちなみに尾白の湯は「名水公園べるが」というアウトドアアクティビティの付属施設である。確実に到着するため、名水公園べるが行きの看板にしたがう。
午前10時25分、名水公園べるがに到着。
到着直後のぐるぐる・・・。名水公園べるがはただの公園ではない。
キャンプ場、BBQ場、グランピング、遊具つき公園も備える広大な敷地は20万平方メートルもあるのだという。
それゆえ「尾白の湯」の玄関前に到着するまえに公園内をぐるぐるさせられる。それもなんと車で。
公園内は木々に覆われていてたいへんに心地よい。低いところに生える艶入りの葉はシャクナゲ。シャクナゲがたくさん植えられているあたり、ここは春のシーズンも楽しみなスポットだ。
生えている木々の下を通り、レンガの道を踏み、森の中のハウスを見、場内をぐるぐるしながら行くとようやく「尾白の湯」の建物を見ることが出来た。
午前11時、尾白の湯に到着。さっそく館内に入る。
館内、公園のぐるぐるに反してこちらは直線的。エントランスのある棟から温泉設備のある棟に向かう途中、渡り廊下がある程度で建物はかなりシンプルな作り。
しかしながら、シンプルさのなかにある窓の多さ、エントランス棟の天井の突き抜けるような高さ。これらのおかげで館内は非常に明るい。
南向きの玄関から入って、最奥部の浴場にいたるまでずっと明るいという印象。浴場は北向きながら、やはり高い天井にともなう採光がとれていて、まったく暗いという感じがしない。
露天風呂へは内湯側からドアを開けて行く。ドアを開けた瞬間、猛烈な寒さに襲われたが、それに耐えて眼前に絶景の山を見た。山は八ヶ岳。
無色透明の「白湯」と黄銅色の「赤湯」。露天風呂は2種類の湯が楽しめた。
湯の温度は・・・、アレ?温度計が無い。
どうやら、道の駅はくしゅうで湧き水の温度を測った際、どこかへ置いてきてしまったようだ。
シマッタ・・・。
温度計は拾った人に大事に使ってもらうことにしよう。
年の瀬に思ってもみなかった奉納をすることとなった。
厄年くる年。
数えの四十二。
ただでは終わらせてくれないラストのようである。







堤体に向かう
午後0時10分、尾白の湯を出発。堤体に向かう。
本日入渓するのは北杜市内、大武川の支流となる「桑木沢」。大武川といえば今年の3月1日に入っていて、そのときのことは「釣り場のじじい」というタイトルで当ブログに投稿している。
めざす車の駐車スペースは当時と一緒。異なるのはスタート地点というだけ。
名水公園べるがを出発。東側サブゲートから出て南進する。
丁字路を右折。尾白橋をわたるとみちなりに進んだ。
「おっぽに亭こっこ」「北杜市白州運動広場」があるあたりが北杜市白州町横手。横手を過ぎると北杜市白州町大坊。
大坊の丁字路からは、3月1日とまったく同じ道。
篠沢大滝キャンプ場の看板前ではY字分岐をひだりななめ前方へ。大武川の左岸道路を走り、大武川砂防堰堤直前では道がおおきく右にむかってカーブする。カーブにしたがって行き、そのまま林道内へ。林道内、1.3キロほど進んだところで橋。橋の名は「篠沢橋」。
篠沢橋をわたりきり、50メートルほどで林道ゲート。この林道ゲート前は車両の転回場のようになっている。
午後0時55分、林道ゲート前。車は転回場の端に駐車した。








桑の木沢探勝路
だれもいない駐車スペース。
スラックスを脱ぎ、その下に履いていたアンダータイツを脱ぐ。
駐車スペースから堤体までは歩いて15~20分ほど。近すぎず、遠すぎずの距離。ウエーダーを履いて水中を歩いたりするが、それでもアンダータイツ有りでは暑すぎる。
汗をかいてしまっては逆に冷えてしまう。寒い思いをしたくないからあえて脱ぐ。脱いだアンダータイツは車内に置いていくことにした。
上半身もやはり長袖シャツを脱ぐ。ただし、こちらは一時的なもの。脱いだシャツを腰に巻いて、いつでも着込めるよう準備する。
午後1時20分、歩きをスタート。
先ほど車でわたってきた篠沢橋を戻るようにわたり、直後を左折。看板によれば「桑の木沢探勝路」という林道らしい。もう一枚立ててある看板には「篠沢大滝まで徒歩100~130分」と書かれている。
篠沢大滝に向かう人用に開かれた林道ということだ。その名がキャンプ場の屋号になるほどのものなので、よっぽど見事な滝なのだろう。100~130分歩いた者だけ・・・、というところがまた期待感を掻き立てる。
看板を過ぎた直後には、もう1本の橋が出現。こちらは「しるたる沢橋」。しるたる沢橋もわたりきる。
橋をわたりきったら100メートルほどすすむ。すると動物避けに立てられたネット製フェンスがあらわれる。
フェンスには開口部分があり、こちらを開けることによってフェンスの中に進めるようになっている。
篠沢大滝に向かうならフェンスの内部へ。桑木沢に入渓するならフェンスの直前を左に折れる。
折れたところが入渓点。
午後1時半、桑木沢に入渓。上流にある堤体をめざす。
入渓直後、岸沿いに残雪を確認。これを踏んだ瞬間ツルッといくことは稀だが、靴底に付着したりするので注意したい。どんなに高級な靴底だったとしても、雪が付着してしまえば途端に摩擦力を失ってしまう。
雪の上はなるべく歩かないように。それでもルート上、行きたくなったら雪を踏んですすむ。
雪を踏んでしまったあとにはデコボコの岩の上を歩いたり、砂の上を歩くようにした。靴の摩擦力に頼れなくなった分は地面の摩擦力で補う。
陸上、水中、陸上、水中と交互にすすむ。
午後1時40分、「篠沢砂防えん堤」に到着。







水の分散
水はきれいに落ちている。放水路天端を横長にひろく使っているところがいい。
冬期の減水期に入ってしまっているなかでの水の分散。
水量は限られ。しかし左右に満遍なく振り分けられていることによって、印象はやわらかい。
ドサッと一点に集中するような落ち方は重苦しく、音も低周波で心地悪い。
今ここに恐怖心を与えるような、気持ち悪さを与えるような水の重さは必要ない。
堤体の水裏側(堤体の下流部側)に設けられた超速の勾配を白泡ともないながらゆっくり落ちてくれている、やさしい感じの落水は親しみやすい。
しかしながら二段構成になった堤体より下流の区間は、ふたたび荒渓としての厳しさを取り戻す。
落ち込み、強く叩き、大石にぶつかりながら下流へとつづく水のすがたを見せてくれる。
高めに保った視線の先には、親しみやすい堤体。しかしながら、その下流を見れば、また音を聞けば、決してやさしいだけの渓では無いということがわかる。






鳴ったり鳴らなかったり
自作メガホンをセットし、声を入れてみる。
音は鳴ったり鳴らなかったりという展開。
堤体の縦横の大きさ、左右両岸高く続く斜面。大場所と言って間違いない堤体前は谷の左右両岸が開き気味で、音が逃げていく印象に強い。
もっと空間が閉じていて、音が残ってくれるような形状であれば響きが得られやすいはずだ。
真上の空に向かって、左右斜め上の空に向かって。空隙にむかって声を入れていってもやはりなにも帰ってくるものがない。
時折、音が響いてくれるのは風の影響か。
悪いもので、響き=風みたいなイメージができあがってしまっている。
空気が動いたタイミングで響きが得られたという経験は多い。しかしながら、この篠沢砂防えん堤堤体前は両岸が開きすぎている。
見た目から受ける印象がかなり難しい堤体前。しかしながら、うまく鳴ってしまう瞬間があるので逆に戸惑う。
結果として音は響いてくれている。けれども、その理由が不明なため、なんとも釈然としない感じだ。







無事に完結
結局、この日は午後3時50分まで堤体前で遊んだ。
堤体前にたどり着けたこと。
堤体前に立って歌えたこと。
歌い終えて、帰ってこれたこと。
一連の行動が無事に完結でき、良かった。
ことしも一年、堤体前という空間に通って歌うということをくりかえした。
大きな堤体から小さな堤体まで。砂防ダム等堤体類というものがバリエーション豊富にあるなか、いろいろなところに出掛けることができた。
また、その旅のほんの一端ではあるが、こうしてディスプレイ越しにいろいろな場所を紹介することが出来た。
不思議なもので、こんなところがあるよ。と、さまざま書いていくなか、自分自身にも気づきというか学びのようなものが生またりして、いろいろと勉強することが出来た。このことがまた、幸せなことであった。
山のことは山の人たちがうまくやってくれているだろう。
川のことは漁協の人たちがうまくやってくれているだろう。
生態系のことは研究者たちがうまくやってくれているだろう。
すでに報道にあるとおり、希望的観測ふくめた街の人たちの思いは、残念ながら実体に即してはいない。
高齢化とか公金の不足とか規制の甘さとかいろいろなことが言われているが、しかし、一番ヤバいなと思うのはやっぱり、
人がいないこと。
人がいないから何も語られなくなっている。良くない出来事が起きているのに、それを知る人がいない。知らないから、伝えられない。逆に、良いことが起きているのに、それが知らされない。拡散されない。
人がいて、見ていなければ絶対に対策には繋がらない。
山に川に人が来られるような仕組み作りは、早急に解決されるべき課題である。
自身においては引き続き、砂防ダム等堤体類を使った遊びとして音楽というものを薦めていくこととします。
堤体前の広い空間で歌う気持ちよさ。
その快楽、その欲望に火を付けるような文章がもっと書けるようになれば、フィールドはもっと良くなるかもしれません。
本年もありがとうございました。
来年もまたよろしくお願いします。