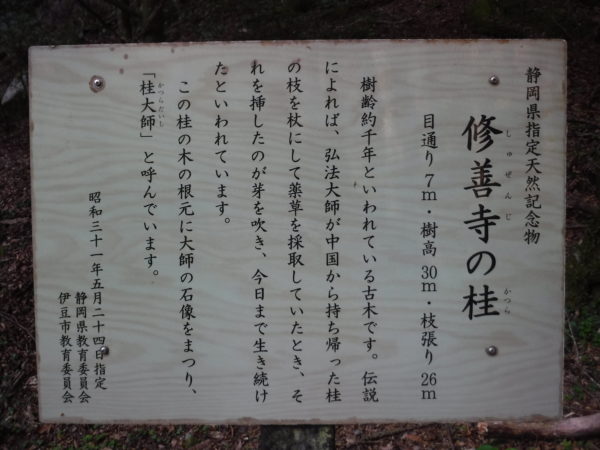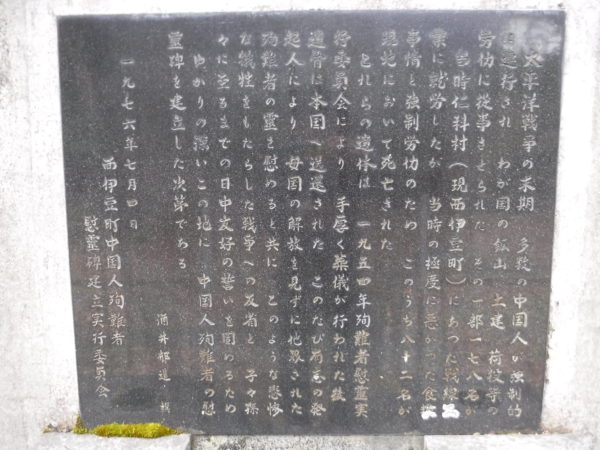私は普段、副業先のホームセンターで砂防ダム音楽家であるといろいろな方に説明した上で働かせてもらっているのだが、ある日このような質問を受けた。
―なぜ、滝ではなく砂防ダムなのか?-
これは、私の年下上司であるヨシキ氏からの言葉である。当ブログをご覧になってくださっている方で同じような疑問を持っている方も、もしかすれば多いのかもしれないと思い、今回その点について解説しようと思う。砂防ダム行脚を含まない記事になってしまうが、お許しいただけるのであれば、どうかお付きあい願いたい。

滝ではダメなのか?
まず、滝ではダメなのか?ということについてだが、こたえはNo!である。滝というものがその場所に存在するようになった背景は様々な要因があり、滝にも様々な種類がある。様々な種類とは、ここでは滝本体の周辺環境、周辺空間のことを言っていて、その現場の状態によっては、砂防ダム同様の“価値”が認められ、砂防ダム同様に音楽が楽しめるのである。このような言い方をすると多くの滝愛好家からお叱りの言葉を頂戴してしまうかもしれないが、音楽家の私自身にとっては、滝と砂防ダムでは、砂防ダムの方が価値が高く(これまでの経験上、素晴らしい砂防ダムに多く出会ってきたため。現在では。)、できればそちらを目指したいという意欲が勝っているのである。

砂防ダムの音楽を始めた頃のはなし
現在、自分自身としては滝よりも砂防ダムの価値が高い。としたが、砂防ダムで音楽をするようになったそのはじめの頃はどうであったかということを述べさせていただきたい。時は2016年の夏頃であったと思うが、人生で初の砂防ダム体験を経験した私は、その魅力にどっぷりとはまってしまい、砂防ダムという、水が直下に流れ落ちるというその景観、音響環境から、「滝」というシチュエーションの中でも同じように、楽しい音楽体験が出来るのではと、滝めぐりをしたのであった。ネット上のブログなどで滝に関する情報を得ては、その場所へ出向き、滝を見つけ、声を出したり、歌ったりして、ここで音楽が出来るものなのかどうか?ということを考えたものである。そう、いま思うと考えたり、悩んだりすることが多かったように思う。
滝めぐりをしてわかったこと
滝めぐりをしてみていろいろなことがわかった。まず、前述の通りインターネット上のブログなどの情報を頼りに、様々な滝を見てまわったのだが、そこは全て、インターネット上の“電子活字”で語られる“名前のある滝”であった。ゆえに滝本体が観光名所として開発された場所にあるものであったり、滝そのものが寺や神社などの伝説物やご神体として、崇拝の対象となっているものであったり、私の住む沼津市と隣町である長泉町境にある「鮎壺の滝」のように周辺が公園として整備された滝であったりと、とにかく多くの人が往来するような場所が多かった。そのせいもあって、滝というものに対して“公共の場”というイメージがついてしまった。私自身は前述の通り、いの一番が砂防ダムであったことから、砂防ダム行脚と平行して滝めぐりをしていたため、人がほとんどいなくて、好き放題、声を出して歌える砂防ダムへの比率が徐々に高まっていったと思う。砂防ダムを目指すことになった理由の一つに、人がいない、ということがあげられると思う。
砂防ダムに決めたわけ
そのようにして、滝に行ったり、砂防ダムに行ったりを繰り返していたのだが、あるときの砂防ダム行脚をきっかけにそれ以降砂防ダムばかりを目指すようになったのである。その日のことについて記したいが、細かいことについては記憶上曖昧な面もあるため、ご容赦いただきたい。時は2016年の秋頃の話しで、場所は伊豆半島、沼津市旧戸田村(へだむら)井田川での体験であった。時間帯としては夕暮れ~日没前後という条件であったと思う。県道17号線より、井田川を上流方向に入っていったところすぐに、堤高4メートルほどの小さな砂防ダムがあり、その堤体下流30メートルほどのところに私は降り立った。ここへ来た理由としては、以前この場所に一度来て堤体の写真撮影を済ませていた(なぜ、最初の訪問時に気がつけなかったのかは不明。)にもかかわらず、デジカメの操作ミスでメモリーを全削除してしまい、畜生と思って当地を再訪したのであるが、その日いちにちの終わり、一日の締めのつもりで声を出してみたのだと思う。滝やら砂防ダムやらをあちこち巡りまわり、それでもはっきり「これだ!」というものを見つけ出せず、自分のそのさき将来に不安を感じながら、そして今日も日が暮れて一日が終わりゆくのだ。とでも思いながら、人生、途方に暮れながら、の歌であったと思う。
驚きと発見
するとどうであろうか。自分の声がワァーと響くのである。砂防ダムという空間で音を響かせられるのか半信半疑であった当時であったと思うが、「間違いなく、ここは響くタイプの砂防ダムだ。」という確信を持った瞬間であった。現場は砂防ダムを取り囲むように広葉樹の渓畔林が押し寄せ、奥行きもあり、下草もうっそうと生い茂った夏の季節の出来事である。今となっては砂防ダムの音楽に、その左右を取り巻く崖や渓畔林の存在が必要不可欠であることが当たり前の事実となっているのだが、その当時は、そのことをよく理解していなかったため苦労したと思う。そして、「ここは、いままで行ってきた場所とは違う。山の木々が音を響かせているのだ。音を響かせるためには木々の生えたところに行かないと行けないんだ。」と気づいた瞬間でもあった。

そのような体験から
それ以降に関しては私はほとんど滝に行くことはなくなり砂防ダムばかりを目指すようになった。旧戸田村井田川での経験は自分にとって宝物になった。砂防ダムを見るときはその左右を取り巻く崖や渓畔林を重視するようになり、音がうまく響かせられないときにはまず堤体よりも山の斜面や木々のことを考えるようになった。滝というのがダメなのではなくて、滝の周辺環境、砂防ダムの周辺環境を比較していったときに川をせき止める形で造られた砂防ダムの方が結果的に優れた空間を多く作り出している。ということなのだ。ヨシキ氏の―なぜ、滝ではなく砂防ダムなのか?―という問いに対しては、―砂防ダムでも滝でも良いがどちらかと言えば砂防ダムで、それはなぜなら私が音楽空間の善し悪しを判断するときに、その滝本体、その砂防ダム堤体本体だけでなくその周辺環境全体として見て、判断して、砂防ダムの方が音響的に優れた場所が多かったから。―ということになる。