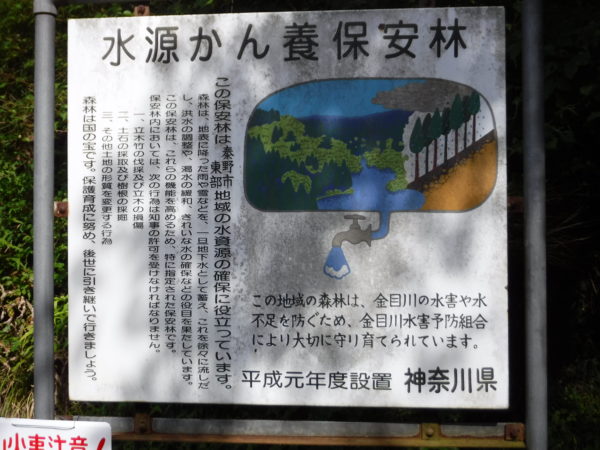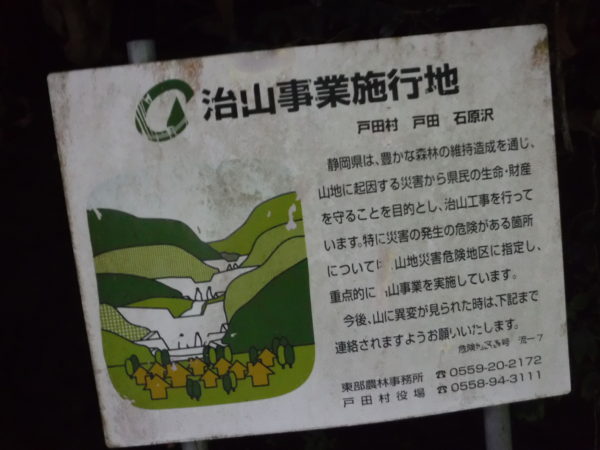7月ももう終わりになるが、今年に関して言えばそれはそれはもう酷い梅雨の1ヶ月であった。先月の第二週(7日)に梅雨入りした静岡県であるが、6月中は驚くほどの空梅雨。ところが一転、7月に月が変わってからは雨または曇りの日が何日も続き、スッキリ雲一つ無い日というのが全然来ないなどという事態をむかえた。いったい今年はどうなっているのだと思いながら時は過ぎ、そして月末。晴れた日はほとんど無かったように記憶していたので念のため調べてみたのだが、7月の第一週はその期間6日間とも雨または曇り、第二週は10日水曜日のみ晴れ、第三週は17日水曜日が時間帯によって晴れ、第四週は25日木曜日が晴れでその前後、24日と26日は時間帯によって晴れ(ⒸNTT Resonant Inc.goo天気より7月28日現在)であったという。なんとこのgoo天気によれば丸一日晴れた日というのは10日と25日のたった2日間のみであったという事である。記憶に間違いは無かったのだ。
選択性の高い現場
そんな2日間の晴れのうち、25日に行った砂防ダム行脚について紹介しようと思う。場所は伊豆市湯ヶ島の河原小屋沢。河原小屋沢と言えば以前当ブログでも紹介した猫越川の支流河川である。現場へのアクセス方法も、猫越川の右岸側林道に車を停めてから猫越川橋を歩いて渡りきるまでは同じ。そこから猫越川の堰堤に入る場合は林道を右側に外れれば良いし、河原小屋沢に行く場合はそのまま林道に沿って歩けば良い。このことはとても便利で、例えばある日、車で猫越川の右岸側林道まで車で走ったとして、それからその日その時の気分によって、猫越川に入ろうか河原小屋沢に入ろうか決めれば良い場所なのである。選択性の高い現場だと言えるであろう。

ヒグラシについて思うこと
25日夕方、猫越川右岸側林道の道幅の広くなったところに車を停める。ここは以前にも書いたが猫越川橋以前に駐車スペースが無いため、いったん林道に入り、道幅の広くなったところに駐車する。スギ林の木の下で、車のエンジンを止めるとtr~(Ⓒ鈴木輝昭 ひぐらしのモチーフより)と鳴く野生生物の声があちこちでこだまする。初夏のセミ、ヒグラシの鳴き声だ。このヒグラシというセミに関して、俳句の季語ではどうやら初秋のセミとして扱われているようであるが実際、生息をするのは初夏である。日本全国の森を出歩いたわけでは無いため初夏にしかいないとは断言出来ないのであるが、少なくともヒグラシの生息の最盛期は初夏で間違いないことが自分の経験上のものから解る。山間地というほどの高い山の中で無くても生息していて、しかもこのセミはどうやらスギなどの人工林が大好きなようなのである。したがって、街場に住む人にはあまりピンとこないかもしれないが、ちょっと村地寄りな場所に住む人にとっては身近な存在であり、日本各地のそういったところで、人に、野生動物に夏の訪れを自身の鳴き声によって伝えてくれるいわば告知者となっていて、であるからこそもっと多くの人が正しくこの生物の生態を理解し、文学に取り入れていくべきでは無いのか?と、思うのだがいかがであろうか。まぁこの今年の異常気象ともいうべき空梅雨&長梅雨の中で元気に鳴きまくっているその声が聞けたこと、これには安心した。
安全なところを降りる
さて、目的の河原小屋沢の砂防ダムであるが、猫越川の右岸側林道から歩きはじめ、猫越川橋を渡ったのち、そこから10分程度歩くと到着することが出来る。砂防ダムの堤体前すぐの区間は、川の直前で結構切り立っており危険なためそれより以前の所の斜面を降りる。堤体前100メートルくらいにちょうどスギの木が途切れた区間があり、そのあたりから降りると上から下まで坂になっていて安全である。立木など掴まるものが無いので、ウォーキングポールなどで体を支えながら降りるとより安全だ。

ヒグラシと競演
ここの砂防ダムは堤体前がちょっと明るくなっている。左右にはしっかり渓畔林が入っているのだが、横方向の懐が比較的広いため、それに覆いかぶさりきることが出来ず空から光が直接差し込んできている。音楽を楽しむにあたっては堤体を流れ下りる水に魅了されてついつい前に立ちたくなってしまうところであるが、そこをじっとこらえて50メートル以上後方に下がる方が良い。日の光が直接降りてきているところは左岸側にいくらか堆積している土砂を観察すれば微妙な違いも解るので、いろいろ見ながら、少しでも暗くなった場所を選んで立ち位置とすると良いと思う。また、この場所は盆栽岩(勝手に名付けた!)があり、なかなか見事である。岩の下部を河原小屋沢の清らかな水がへつるようにして通過していて、寄せ植え樹形盆栽の“静”と水の“動”が融合されたなかなか見事な光景であるように思うのだが、いかがであろうか?是非とも専門家の意見をお伺いしたいところである。私自身においては、そんな盆栽に触発されて、フーゴ・ヴォルフの「庭師」を高らかに歌い上げた当日であった。それはしかも初夏のセミ、ヒグラシとの競演であった。