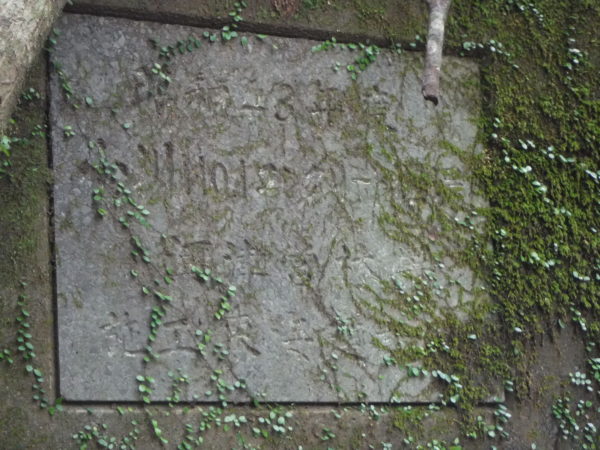今回の記事は先月、当ブログに書いた「ハウスみかんを獲得」の続編である。そのとき使用した沼津市内浦~戸田峠のルートを今回、実際にたどって砂防ダム行脚にチャレンジした。
9月25日、炉端焼き店のアルバイトを終え、その後自宅に戻り就寝。翌26日は午前8時に起床した。この日はホームセンター、炉端焼き店とともに仕事が休みであったためゆっくりとした朝であった。布団をたたみ、服を着替える。本日目指すのは、自宅と同じ沼津市を自治体とする沼津市戸田。自宅と同じ沼津市・・・、と言ってもその目的地までの道のりは長く、一時間以上を要する。また本日は、内浦重須(うちうらおもす)でみかんを買ってから、現場を目指すという予定を組み立てていた。けっして急いで現場に向かう、という感じではない。ゆっくりとした行程で、残り少ない夏の日を満喫しようという算段で自宅を出発した。
緑色みかんを獲得
沼津市内、千本浜の松林を走り、沼津港前を通過したのち港大橋を渡る。玉江町交差点を右折し、国道414号線に入る。それから島郷、静浦へと続く。9月ももう残すところあと数日であるというのに、今日もまた暑い。途中、右手に見た静浦の防波堤上には多くの釣り人が並んでいた。ここは、静岡県内屈指の人気釣り場である。本日は穏やかであるが、連日の台風報道で釣り場の様子はいかがなものかと心配していたが、その必要は全く無用であったようである。今日の日の夏の暑さを満喫しているようで、そんな心配はかえって魚が散ってしまう余計なお節介であった。静浦を過ぎその後、多比第二トンネルを抜け「口野放水路交差点」で右折、道は県道17号線に入る。「マルカ」にはあっという間についた。露地栽培ものの緑色みかんは台の上の左側の方に並んでいた。車を降り、すぐさま狙いをゲットする。一袋500円。緑色・・・。と、みかんの色を形容するのは、いささか違和感を感じるかもしれないが、これはもう確実に緑色である。太陽の光を一杯に浴びて育ったこの地のみかんが放つその緑はたいへんに力強い。青々としている・・・、などという“国語的な”言い方はふさわしくないように思えるのだ。ようやく大好物の「緑色みかんを獲得」である。

少し変わっている。
「マルカ」を出発し、西浦木負の丁字路を左折する。この海抜わずか数メートルしか無い西浦木負から標高およそ700メートルの戸田峠まで一気に坂を登る。その前半戦はみかん畑地帯といった感じでそれなりに人影を感じるのだが、途中にある「←戸田峠4.8km」の看板以降の後半戦からは少し変わっている。両側二車線で全区間、センターラインの引かれたきれいなアスファルトの道が続くのだが、その道路の綺麗さに反して交通量が極端に少ない。というより、なにも走っていない。超閑散としていて異様である。道路を管轄する側はそのことを知ってか知らずか?どうであろう、どうせ車なんてほとんど走らないから、とばかりに道路の幅の両端に積もった落ち葉を片付けること無く放置したりしている。また、明らかに車道の建築限界を侵している樹木の枝も剪定されること無く放置されているし、いったいこの道路は何なんだ!?と言いたくなる異様さである。そして最後のトドメ!2本の電灯の全く点いていないトンネルをくぐり抜けると戸田峠すぐの十字路に出るので、ここで登り坂が終わる。ここから戸田方面に行きたい場合は右折、修善寺方面に行きたい場合は左折する。今回は戸田に行くため右折した。それにしても、異様な道路である。異様なオーラを放ちすぎて、これは嬉しいことなのか?ゴミすら全然落ちていないのであった。本当に通りの少ない道路なのであると思う。


御浜岬
戸田へは途中の寄り道が少なかったこともあって午前中のうちに到着した。あまりの暑さに、日が高いうちの現場入りをあきらめ、午前中は戸田もてなしの里公園、午後は、御浜岬周辺でそれぞれ過ごした。御浜岬では、外海側にも戸田湾側にも静浦同様に釣り人がいてキャストをくり返していた。ベタナギの海から照り返される太陽の光を浴びながら私も釣り人も残り少ない夏を満喫したのであった。




残り少ない夏の日を満喫したのであった。
午後4時。現場に入るため戸田大川に沿って県道18号線を東へ進む。戸田大川の右岸沿いをこの県道18号線に従っていくと最後、「達磨橋」という橋で対岸側に離れるのだが、そのまま右岸側をキープするように直進し、林道に入る。この林道に入った地点からおよそ300メートルのところにY字の分岐があるため、その分岐周辺に通行のじゃまにならないよう車を停める。ここの入渓点は竹ヤブだ。Y字分岐よりわずかに山側、そこに「落石注意」の看板があり、その看板から約10メートルほど手前の竹ヤブを降りる。竹ヤブは密度が濃く、降りにくい所であるがほどなくして戸田大川に降り立つことが出来る。当日は午後5時から短い間であったがここで音楽を楽しんだ。夏の夕暮れ時の歌は特有の風情があって良い。竹ヤブを降りてくる時に、待ち構えていた蚊たちを刺激してしまったのか顔のあちこちがかゆい。こういった特有の風情も蚊たちの猛攻も、あと1ヵ月もすれば失われゆくであろう。今はまだそのことには気づかない。今日の日の日中に襲われる暑さにブーブー文句を言い、顔がかゆいと小さな虫を相手取って恨んだりする。そのことの幸せに全く気がついていないのだ。川に入って1時間後の午後6時、限界の暗さになり終了。―夜のおとずれもずいぶん早くなったものだ。―その後、戸田大川を上がり、再び戸田港方向に向かって車を走らせた。今日は一杯汗をかいた。その汗を流すべく、道の駅「くるら戸田」内にある温泉「壱の湯」を目指したのだ。
温泉から上がり、入り口にある自動販売機でつめた~いジュースを買い、一気に飲み干す。ほかの温泉客も地元民と見られる人たちも、あぁ、いい湯だったと満足げに帰って行く。私もほかの方たちも家族連れの子どもも皆、半袖という出で立ちで通過する「くるら戸田」の正面玄関であった。