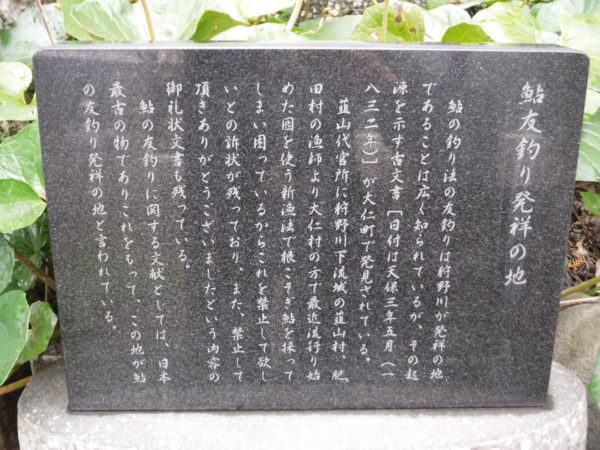自分が蛍光ペンというものの存在を初めて知ったのは小学校の頃であったように思う。同じ町内の子どもが集まって、バスハイクと呼ばれる保護者会の計画した場所へみんなで遊びに出掛けるという行事が、毎年、夏休み期間中などに行われていたのだが、そのバスハイクのビンゴ大会の景品として、自分の手中に収められたのが蛍光ペンとの最初の出会いであったように思う。景品の入った袋を開けると、ほかの鉛筆やらボールペンに紛れて、黒いボディにオレンジや黄色の鮮やかなリングがはめられた、見たことの無いサインペンが入っていた。文房具という本来、主に屋内で使用されるはずのそれは、バスハイクの行き先である森林公園という環境下、とても鮮やかに光り輝き、少年たちを大いに騒がせた。兄や同級生の中に混じって私は、「なんだこれは?」となっていた。
景品担当
バスハイク本体がどこへ行くか?何をするか?昼飯は?配るおやつは何なのか?といったことは全て保護者会の役員によって決められる。自分は当然、子どもであるからそこに参加するだけなのであるが、今思えばその行事に関わった保護者会の役員たちは大変な苦労であったと今更ながらに思う。何十人ものやんちゃな子どもたちを引き連れ、自分たちですら慣れないところに連れて行き、楽しませ、食べさせ、最後、朝の集合場所に子どもたちを降ろして終わりなのでは無く、そのあとしっかり無事に家までたどり着けるように導いてやらなければならない。ビンゴ大会の景品担当一つにしたって、品物は子どもが喜んでくれそうなものを選びつつ、親が見ても腑に落ちるような内容で無ければならない。バスハイク中のエピソードなど直後は甲高く大いに語られるかもしれないが、通常2~3日もすれば子ども、親ともに記憶の中からほとんど消し去られ、忘却の言葉と相成るはずであるが、ビンゴ大会の景品という“形あるもの”は、それがいつまでも証拠として残ってしまう。蛍光ペンはじめ、文房具各種を買いに走った景品担当の苦労というのは、肉体的なものに留まらず、精神的なものも伴っていたであろう。意外と、そういう仕事というのは周りの人間が大して気にしていないのに、本人は「何を選んだらいいだろうか?」と必要以上に気を遣っていたりするものなのである。
見てきたもの
そして今、砂防ダム音楽家となっている。当時は、夏休み中一回きりの森林公園での山遊びであったがそれが一年中、山というところに行くようになり、その山という所での四季、いろんなものを見てきた。ベストシーズンの枯れきった冬山、新緑の春、うだるような暑さの中で生命が躍動する夏などどれもがおもしろく、魅力的である。これからのシーズンは紅葉が楽しみだ。自分は砂防ダム音楽家としてまだまだ経験が浅く、未熟だと思っているが、その少ない経験の中で見たところを紹介しようと思う。

またしても
場所は持越川上流域。中伊豆、湯ヶ島温泉街を伊豆市市山のあまご茶屋前から入り、道なりに進むとやがて猫越川に寄り添う形になるが、これに沿ってさらにしばらく進むと「水抜橋」というガードレール製欄干の橋に出られる。その水抜橋の直後には丁字路があるので右折し、5キロほど道なりに進むとISO14001認証取得工場という大きな看板が現れる。これは中外鉱業(株)持越工場の工場看板で、その中外鉱業を右手に見ながら橋を渡り、さらに進んだあたりが紅葉の美しいエリアである。「小沢橋」の前には堤高3メートルほどの低い堰堤があり、その堰堤のちょっと上流に行ったところには小さな滝などもある。濡れた川石の黒、渓畔林の暗さから生じる黒。黒の中で様々な落葉樹によって放たれた色が鮮やかに光を返す。
「なんだこれは?」となっていた。最初に見た時。その色はまさに小学校の頃、バスハイクのビンゴ大会で手にした蛍光ペンの色と同じであったのだ。自然界の作り出した黒の中にこれまた自然界の作り出したオレンジや黄色の蛍光が光り輝く。今度はペンの状態で無くてキャップを外して、実際に塗った色だ。いや、規模の大きさから言えば、塗った。とかじゃなくて、蛍光ペン工場にあるであろうインクの入った大きな缶からバカでかい刷毛で塗料をぶちまけないと、この量はまかなえない。などと思ったりした。





紅葉は見てのお楽しみ
本記事では自分のまだまだ少ない山経験の中からも、特に印象的であったこの場所を紹介している。同所の紅葉がとても美しいのは堤高3メートルほどの堰堤と、その上流の小さな滝が影響していると思う。ふだんあちこちの砂防ダムに行っていて、砂防ダムや砂防堰堤周辺には気流が発生することを私は経験の中から心得ている。砂防ダムというのは二階部分から一階部分に向かって吹き下ろす形で空気は流れる。例えば夏場、二階部分に溜まった土砂が太陽光の熱で温められているような環境だとその風はいっそう強い。沢を流れる冷たい水と温められた土砂の温度差で局地的に気流が発生するのだ。樹木の形状が変化する「風衝」ほどの変化は見て取れないが、葉の生育程度にはこの風は影響を及ぼし、紅葉の色がよりはっきりしたものになるのだと思う。
以上の理屈は私なりの勝手な持論だが、それにしても蛍光ペンという化学工業製品並みの色を自然界の環境が作り出してしまうことには大変な驚きを覚える。毎年、毎年忘れること無く色づく植物において、これは原理に基づく物理的変化だと言われても、生き物としての意思を持った作為による発色なのだという感を受け取らざるをえない。
この持越川上流域はトイレさえも無いような観光設備ゼロの無名渓谷であるが、その点含め大変魅力的であるので同地への訪問をおすすめする。尚、実際の紅葉の姿は見てのお楽しみの画像なしということでご了承いただきたい。