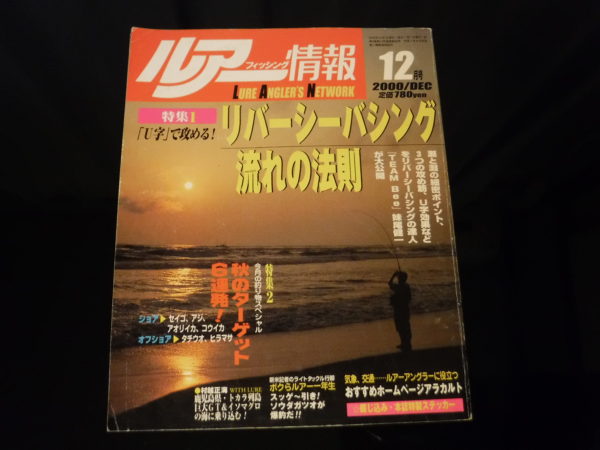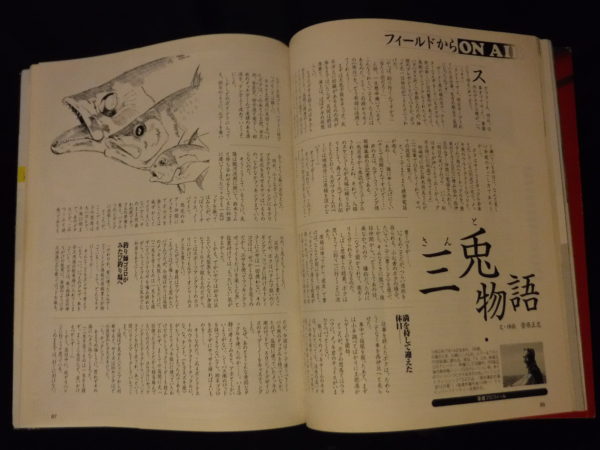ある日のこと。ホームセンターにて箒を使っているとなにやら出所不明の赤い実を見つけた。大小ごちゃ混ぜの泥まじりの落ち葉をガサガサとどかしていると、ひときわ目立つ“赤玉”が一つ、シダ箒にはじかれてコロコロと転がった。
これは何の実だろうか?
ふと、周りを見渡す。ん?
気がつけば周囲には、赤い実をつける植物がそこかしこに。確かめてみればヤブコウジ、センリョウ、マンリョウ、ナンテン、ウメモドキ、オウゴンモチ、チェッカーベリー、セイヨウヒイラギなど。今の時期は、クリスマス&正月前のシーズンとあって、売り場は赤い実をつける植物だらけであったのだ。
いろいろ見比べてみた結果、赤い実はチェッカーベリーの実であることが判明した。

そういえば
そういえば、あの沢の流域には赤い実をつける低木がたくさん生えていたな。と思い出した。神奈川県足柄下郡、湯河原町を流れる藤木川の支流にアケジ沢という沢があって、そのアケジ沢の流域にはどういうわけか、その赤い実をつける低木がよく生えていたのだ。低木の名前は不詳。
―わからないときは調べなきゃ。―と思いつつも、砂防ダム探しに夢中になっているとついついこんなことをしてしまう。図鑑をパッと開けば答えが載っているというのに、上に行くことばかりに心酔していて、同定作業が疎かになってしまっていたのだ。
売り場でふと考えた。もちろん結論としては、その赤い実を調べに行くということ。湯河原行きを決定した。尚、今回はすでに行った事のあるアケジ沢を最後まで行くのでは無く、途中から合流する支流の「勘三郎沢」に移って遡ることにした。つまりのところ新規開拓。勘三郎沢はほんの一部であるが、箱根-湯河原間をつなぐ自動車専用道路「湯河原パークウェイ」と並行している区間があり、じつは以前、この湯河原パークウェイを走行していた際に上から覗き込むようなかたちではあるものの、2本、堤体を発見していたのだ。以来ずっと行って、下からも見てみたいと思っていたのだが実現できていなかったため、今回はその確認作業となる。
クリスマスイブ前日の12月23日。行くなら今日だと経由地の箱根峠を目指した。

シーズンを迎えていた
23日午前9時すぎ、「箱根峠」信号を南東方向に右折し、「湯河原峠」バス停直後にある湯河原パークウェイ料金所を目指す。途中、道端が白くなっていたので車を止めてよく見れば、なんと雪。前日、沼津市内では雨が降っていたが、この地ではもう積雪シーズンを迎えていたようである。再発進しバス停前を通過。左折してすぐにあるパークウェイ料金所にて通行料金を支払い、坂を下りはじめる。
「エンジンブレーキ併用!」の看板が示す通り、ここの坂はなかなか勾配がきつい。本格的に雪が降ってしまえば、通行止めの措置がとられるそうであるが、そんな状態にあっては、そもそも坂を下りることがはばかられると思う。
―昨日じゃ無くて良かった・・・。―などと思いながら坂を下りていくとあっという間にパークウェイが終了。奥湯河原温泉街に出た。その後「加満田」の看板前丁字路を右折。車が入っていけるところまで入っていくと入渓点が現れた。

群生しているのか?
―あった、あった。―アケジ沢の入渓点に表れたのは記憶にあった通りの赤い実。粒の大きさはアーモンドの種くらいあって、店にあるものたちよりも細長くて大きい。早速図鑑で調べると、アオキの実であることが判明。
それにしても、このアオキの実たちはこんなにも堂々と空に向かって「どや!」とアピールしているのに、野生動物の食害をほとんど受けることも無くきれいに残っている。アケジ沢の流域のみならず奥湯河原一帯に広く群生しているのか、ターゲットになりにくい環境にあるようだ?しっかりとした赤で、これだけの粒と色を出すのには、さぞかし体力を使ったことであろうと思う。ちぎり取られる痛さはあるかもしれないが、頑張った甲斐も無く散布の恩恵を受けられないのは、不本意なのではないか?
アオキの画像を撮り終え、時計を見れば午前11時。準備を済ませスタートする。橋を渡り直後の堰堤を巻いたあと、ここで初めて水に入る。昨日の雨(雪)の影響もあって、水量は豊富だ。水道用の水車小屋がある前の堰堤を巻いたあと、次の堰堤も巻き、合流点に差しかかった。



右側の沢へ
直進がアケジ沢、右側が勘三郎沢。過去には直進して砂防ダムを見てきたことがある。藪を漕いだり、大きな滝があったりなどしてかなりきつかった思い出があるがそれだけに、今回の勘三郎沢もかなり手こずるのではないかと緊張する。
午前11時半、緊張と新規開拓の期待感とともに勘三郎沢に入る。合流点すぐの低い堰堤を巻き、進む。川の規模としては沢と言うにふさわしい具合。こんな沢を上がっていって本当に砂防ダムがあるのかとも思うのだが、今回は堤体そのものについては確認が取れている。幅の極めて狭まった区間からは「渓谷」の感が強く感じられるが、パークウェイから投棄されたと思われるゴミが散乱していたりする所には不気味さを感じる。
勘三郎沢に入ってから40分ほどの行程で、画像Ⓐの砂防ダムに到着。なかなか雰囲気は良かったが、今回の目的地はパークウェイ沿いの2本と決めていたためここでは歌わずにパスすることとした。



1本目の砂防ダム
Ⓐの砂防ダムを越えると、目的の砂防ダムはもう近かった。パークウェイ沿い1本目の砂防ダムの登場である。堤体に幾つか開けられた水抜き穴の一番下から水が流れ落ちていて透過型砂防ダムとして機能している。もはや排水口に近い。これでは音楽など楽しめないと画像を撮り終え、すぐさま堤体左から巻き始める。かなり手こずったが登り終え、天端上の右側に移ったあと堤体の上流側側面をおりる。透過型砂防ダムというのは滞留土砂を持たないため、堤体を巻くときの後半に降りるという作業が発生し、しかもここでは大変に苦労した。


2本目の砂防ダム
降りきってから遡行を再開し、10分ほどで2本目の砂防ダムに到着。遠巻きに目に入ってきた時、もう理解できていた。パークウェイ沿い2本目の砂防ダムも透過型であったのだ。
ここまで来るのにスタートから2時間40分。当初の予定通りここが本日のゴール地点。そのまま引き返すかと思ったが、せっかくだからとbluetoothスピーカーの電源を入れる。シューベルトのganymedを再生させると、歌えてしまった。途中、
Ruft drein die Nachtigall Liebend nach mir aus dem Nebeltal.
(呼ぶ、そのなかへ、ナイチンゲールが、愛する私に霧の谷から)という部分があるのだが、たしかにナイチンゲールではないものの何かの鳥がピーピーと鳴いている声が聞こえた。選曲はあっていたようだ。
小一時間、水抜き穴から流れ落ちる3本の白いすじを見ながら歌って、楽しんだ。今回は、苦労して上がってきて結果、これであったのだが、残念な気持ちなどは無い。自身の気持ちに対して素直になりここまで来られたと思う。探究心を持って沢に挑めたと思う。新規開拓できたという喜びの方が大きかった。
令和初の年もそろそろ幕を閉じる。来年も元気に積極的に、好奇心旺盛にどんどん新しい砂防ダムにチャレンジしていきたい。