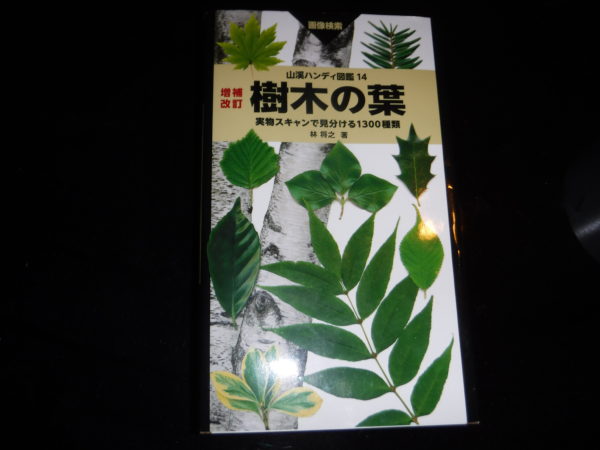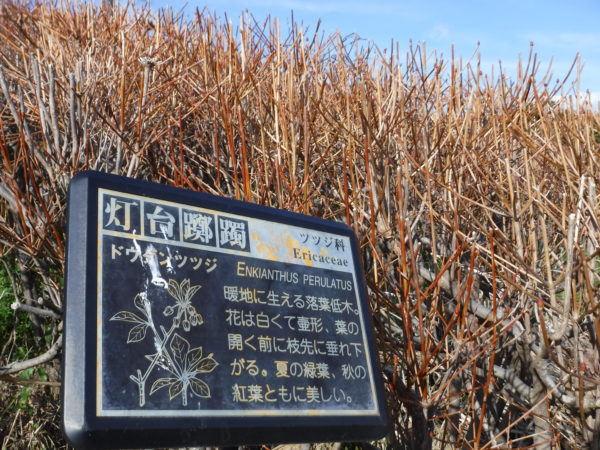上の画像をご覧いただきたい。この場所は河津町河津筏場、多目的広場のトイレ前で撮った一枚。地面を指さして、なにを面白がっているのかと言えば、この一帯に敷かれている砂利が「岩滓(がんさい)」と呼ばれる形質のものだからである。別名をスコリアという。
自分が勤務するホームセンターのエクステリア部門ではこのスコリアを取り扱っていて、お客から訊ねられる事が多い。使い方として、こんなふうに駐車場に敷いたり、庭に敷いたりする目的で買っていくようである。また、ホームセンターという個人向け以上の使用量を要するところには、路盤材として使われるようだ。
多孔質で水分をよく吸収するため、透水性に優れた、つまり水はけの良い舗装路面が出来上がる。なおかつ、その吸収した水分についてはそのまま保持されるため、夏の猛暑の時などは地面の温度を比較的低くおさえる事が出来る。
さらに上の画像にあるような赤色のものであればなかなかおしゃれであるとも思う。グレーカラーの砕石には無い、暖かみのようなものが感じられる。

確認作業
一方でこちらは多目的広場を別角度から撮ったもの。真ん中でデーン!としているのは「鉢ノ山」である。
鉢ノ山もたしか・・・
自宅にある伊豆半島関連の資料を探してみたところ、「東伊豆半島ドライブジオマップ」というパンフレットにたどりついた。DM折りされたパンフレットをていねいに開くと、〔鉢ノ山 3万6000年前にできたスコリア丘(東伊豆半島ドライブジオマップより)〕とある。
やはり鉢ノ山はスコリア丘であったのだ。冒頭の画像だが、スコリア丘を眼前とする多目的広場トイレ前にスコリアを敷くというギャグは誰が考えたのか?と面白がっていたのである。(ギャグじゃないかもしれないが・・・。)

佐ヶ野地区
この鉢ノ山および多目的広場であるが、河津町内では佐ヶ野地区に属する。同町に佐ヶ野という住所は存在しないが、近辺を南北に横断するのが佐ヶ野川でその最下流部には下佐ヶ野、そこより少し上流部には上佐ヶ野という地区がある。
伊豆中央の大動脈、国道414号線が南西方向にカクッと折れ曲がるのが河津町内下佐ヶ野の信号。信号名を言うより特徴的なのがセブンイレブン下佐ヶ野店。そのセブンイレブン前の信号を北東方向に曲がると、佐ヶ野地区に入る事が出来る。
道なりに進めば、あおきフード物流センター、上佐ヶ野公民館、河津浜病院などがあり、下佐ヶ野の信号より3.8キロ地点にあるのが前述の多目的広場。この多目的広場には駐車場があるため(画像を見ての通り。)、鉢ノ山に登る際はこちらに車を停める。
そして、この多目的広場以降のレジャースポットとしては2軒のオートキャンプ場と三段の滝がある。ゆっくり時間を掛けて佐ヶ野を満喫したいのであれば前者、限られた時間の中で名所を見たいというのであれば後者といったところであろう。





左官屋
3月26日、入渓点を三段の滝とし、そこから約1キロほど上流にある堰堤を目指した。この日はスタートが午後になってしまったのだが、その午後の時間は超快晴。太陽が佐ヶ野川の水面をギラギラ照らすなか、遡行する事が出来た。
三段の滝ももちろん見事なのだが、それより上流部もまた見事であるということに気付かされる。一枚岩の上を水が滑り落ちていくナメのヵ所が多く、それらが緊張感を和らげてくれる。滑ってケガをすることも考えられるため、けっして侮ってはいけないナメだが、石の取り除かれた平滑な面を水が通り抜けていくその様を見ていると、どう見てもこれは“人工物に違いない”と思うのだ。
左官屋が来て、きれいに仕立ててくれたのだとしか思えない。足跡の無い渓を歩くことは緊張感を伴うものだが、そうやって誰かが「やってくれた。」と「勘違い。」しながら歩けるなんて、なんて幸せなヤツなんだと我ながら思う。
堰堤には入渓から40分ほどで到着した。



ハイブリッドの堰堤
ここの堰堤は鋼鉄とコンクリートのハイブリッド。鋼鉄が川の下流側に向かってせり出しているため、樹木が引っかかったりすること無くきれいに保たれている。銘板を見れば昭和53年製ということで、私の人生よりも長く生きている。
スズキのジムニーという車に例えれば、SJ型の頃の話しであるから驚きだ。ジムニー、鋼鉄製堰堤ともに現役であったとしてもジムニーの場合はメカニックが介入している。鉄くずと化さぬように自動車整備士の手で大事に大事に管理されたものだけが公道上を今も走り続けているのであろう。
かたや、こちらの堰堤はどうか?佐ヶ野川上流域でほとんど忘れ去られながら時を過ごしている。森林管理局の職員や一部の釣り人などはこの地を訪れるであろうが、そのほかの訪問者はほぼいないのでは無いかと思う。誰の手も借りずに、幾度の嵐に耐えながら生きているということは、その下流の倒木などを見れば明らかなことだ。
bluetoothスピーカーの電源を入れる。選択したのは、シューベルト作曲のLachen und Weinen(D777,Op.59,No4)
本来の歌詞の意味から言えばこの曲は恋歌の一種なのだが、今回私は自分なりに違うテーマを持って歌った。掲げたテーマは「春への戸惑い」。冬が過ぎ、土も十分温まり、命が芽吹く季節を迎えた。
年々、Lachen(笑い)とWeinen(涙)のうち、むしろWeinenが分からなくなってきているような気がする。歳を重ねるごとに様々な経験を積み、対処が出来るようになってきている。
Weinenという言葉をどのように歌ったら良いのか?
春という季節を単純に喜べるようになってきていて、ほんとにこれでいいのか?と思えてしまう。春って、もっと心が不安定になる季節じゃ無かったっけ?
逆にこの有節歌曲2番の後半、
und warum du erwachen kannst am Morgen mit Lachenと歌うが、最後を思い切り「ラッヘン!」と歌えるようになってきている。
完全に自己満足の歌になってきているような気もするが、これでいいと思っている。佐ヶ野川上流部の自然に私の歌を受けてもらっている。そのことに対して感謝の気持ちしか無い。
太陽が傾き、落水を照らしていた直射日光が見られなくなった頃、遡ってきた渓を引き返した。