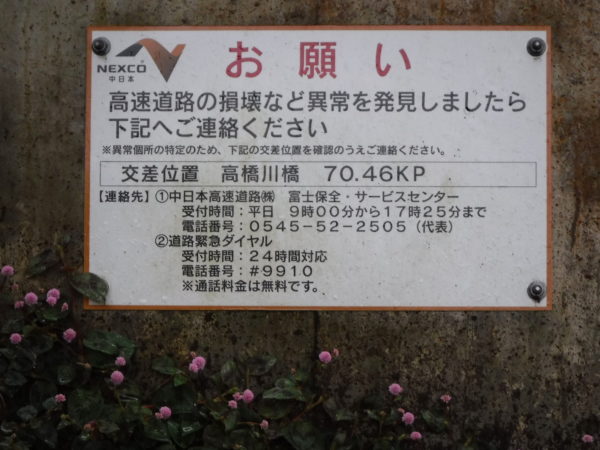砂防ダムの音楽において樹木は大切だ。堤体を前にして立った時、木の無いところでは音が非常に響かせにくい。現状世の中の主流となっている、雑音の全くしない環境(例えば音楽ホールなど。)と違って、砂防ダムの音楽空間では常に水が鳴っているからだ。
主として堤体からの落水の音。そして、そこから先、川石を水が落ちていく音がさらに加わる。滝などがある場合もある。
砂防ダムの音楽では常に川の水の音が、そこで歌う人間の声に抗ってくる。そういった音環境の中で、いかにして音を響かせていくか?というところにこの音楽は楽しさがある。

渓畔林
川の水に邪魔をされながら、いかにして音を響かせていくのかというところには「渓畔林」というものが、大きなヒントになる。自分の身長の何倍もある高さから落ちる水の音に対して、自らの声で戦っていくために渓畔林の力を借りるのだ。
渓畔林とは、渓流の川沿いに生える樹木で構成される林のこと。渓流への直射日光を防いで水温上昇を防いだり、落葉(らくよう)や落下昆虫によって渓流内に養分を供給したり、その落下昆虫が魚類のえさになったりしているというところから、渓流の生態系というものの説明をする際によく使われる用語だ。
砂防ダムについて、これまでいろいろなものを紹介してきた。その周辺環境が多種多様であることは、画像だけ見ただけでも簡単にお分かりになると思う。渓畔林が豊かなところ、そうでは無いところ、様々あるし二ヵ所として同じところは無い。
このことは、本当に面白いことで、例えば砂防ダムの大きさを示す用語に「堤高」という言葉がある。堤高とは砂防ダムの一番高いところである「袖天端」の最上部から、一番低いところとなる「堤底」までの長さをいう。堤高6メートルの砂防ダムなんてそこいらじゅうにあるが、その6メートルの6という数字が一緒であっても、渓畔林が違っていれば響きの面で異なる結果が待ち構えているということがある。
結論から先に言ってしまえば、豊かな渓畔林をもったところのほうが音を響かせやすい。木が音を反射させる性質を持っているからだ。

福士川
ちょっと話しが逸れるが、以前山梨県の福士川上流域に行ったときのこと。その日一日の活動を終え、最後自家用車の置いてあるところまで戻って帰り支度をしていると、林道の上の方から地元林業会社の方が、帰り道すがら私の脇に。なにをしていたかと聞かれたので、
「歌を歌っていました。」
と答えると、
「はぁ、そうだったね。君だったのか。んじゃ、またね。」
と、走り去っていった。
こんなもんなのである。(ちなみに歌っている間はお互い死角の仲にあり、相当離れていた。)
山をよく知っている林業会社の人であるからこその感想であったと思う。山の木のたくさん生えた空間というのは非常に音がよく響く。人の声も、動物の鳴き声も、木を切るチェンソーの音でも何でも音がよく響く。木が音を反射させる性質があるからで、山の人たちはそのことを体験的に得ているからだと思う。したがって、その音が反射する空間で歌を歌っていました。と、言っても別段おどろいたりはしなかったのである。
逆に町場に住んでいて、あまり山や森を知らない人こそ、
「山で歌っている。」
と、言うと・・・えっ???となる。

同定
豊かな渓畔林と書いた。豊かな渓畔林があることは砂防ダム音楽家にとって喜びだ。これさえあれば、川の水量が少なかろうと多かろうと頑張ろうという気になれる。自らの声を補助してくれる装置がそこにあるのだから、それを最大限活用して音を響かせていけばいいのだ。そして、そんなふうに頼りにしている渓畔林に対して、今後も勉強を続けていかなければならないのは当然のこと。
「同定」という言葉がある。同定とは目の前にある植物と図鑑上にある植物を一致させる行為をいう。渓畔林を構成する樹木一本一本を同定し、明らかにしていきたい。今日は声がよく響く堤体に入れました。終わり・・・。じゃなくて、どんな樹種の力を借りて、音楽上の成功が得られたのかをきちんと理解し、経験として蓄積していきたい。
これは現時点でまだ明白ではないことなのだが、同一の堤体周辺で季節によって響きに違いが出てくるような感覚をすでに体験してきている。おそらく落葉樹の葉のつき方が季節によって違ってくるゆえの現象であると仮説化しているのだが、このことが本当であるのか、今後検証していく必要があると思う。
もし、この仮説が合っていたならば、樹種が異なったりすることでその違いはさらに、歴然と、大きなものになるはずである。なぜなら、木は樹種によって、葉の大きさ、形、枝ぶり、幹の太さ等が全然異なる場合もあるからだ。密度、奥行きがほぼ同じくらいの林でも樹種によって響きが異なるというのであれば、これはおもしろい。
そんなところまで行ってしまった先には、砂防ダムを使い分けするような世界が待っている。堤体があってそのまわりにこんな木が生えてます。じゃなくて、こんな木が生えてるところに堤体が一個置かれています。という規模の話しができるようになってくると思う。
違いが分かるようになりたいのだ。待っているのは、一年を通して最強に楽しめる砂防ダム音楽ライフ。一本一本大変な作業ではあるが最終的には笑えるよう常日頃からトレーニングしていきたい。